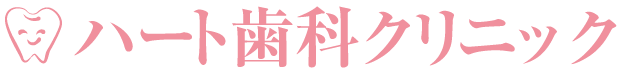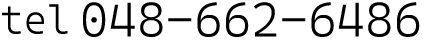歯並びチェック!整った歯並びにしたい!
歯並びが悪くなる原因
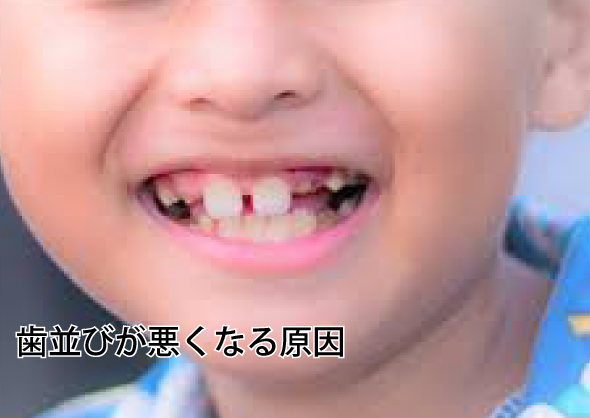
歯並びが悪くなる原因は、いくつかの要因が考えられます。
遺伝的な要因
ご両親から受け継いだ骨格の形(顎の大きさや形など)が、歯並びに影響を与えることがあります。
歯の大きさや数も遺伝することがあり、歯が大きすぎたり、数が多かったりすると、歯並びが悪くなることがあります。
生活習慣
指しゃぶり…幼い頃の指しゃぶりはよく見られますが、長期間続けると、上の前歯が出っ歯になったり、噛み合わせが悪くなる原因となることがあります。
口呼吸…普段から口で呼吸をしていると、口周りの筋肉が弱まり、歯並びに影響が出ることがあります。
頬杖…常に同じ方向に頬杖をついていると、顎の骨や歯に負担がかかり、歯並びが悪くなることがあります。
舌の癖…舌で前歯を押す癖があると、前歯が前に出てしまうことがあります。
その他の要因
虫歯…虫歯が進行して歯の形が変わると、歯並びが悪くなることがあります。
乳歯の早期喪失…乳歯が虫歯などで早く抜けてしまうと、永久歯が生えるスペースが狭くなり、歯並びが悪くなることがあります。
その他外傷による歯の破損や様々な要因があります。
歯並びチェックの重要性
歯並びは、見た目の印象を大きく左右するだけでなく、お口の健康、さらには全身の健康にも深く関わっています。
歯並びが悪くなる原因は様々です。
早期に歯並びの問題を発見し、状況に応じた適切な対応をすることが重要です。
| 見た目の改善 |
やはり歯並びがきれいだと、自信を持って笑顔になれます。 |
|---|---|
| お口の健康維持 |
歯並びが良い状態だと、歯磨きがしやすくなり、虫歯のリスクを軽減につながります。 |
| 全身の健康への影響 |
正しい噛み合わせは、食事の際、消化を助け、栄養の吸収を促進につながります。 |
悪い歯並び例

叢生(そうせい)
叢生(そうせい)とは、歯並びがデコボコで、歯が重なり合って生えている状態のことです。
歯が並ぶスペースが足りないために、歯が正しい位置に生えることができず、重なり合ったり、ねじれて生えてしまったりします。
| 叢生の症状 |
乱杭歯(らんぐいば) |
|---|---|
| 原因 |
顎の大きさと歯の大きさのアンバランス |
| 影響 |
顎の大きさと歯の大きさのアンバランス |
上顎前突(じょうがくぜんとつ)
上顎前突とは、上の歯が下の歯よりも大きく前に突き出ている状態のことです。
「出っ歯(でっぱ)」と呼ばれることもあります。
| 上顎前突の症状 |
上の前歯が大きく前に出ている |
|---|---|
| 上顎前突の原因 |
遺伝的な要因 |
| 上顎前突の影響 |
見た目のコンプレックス |
下顎前突(かがくぜんとつ)
下顎前突とは、下の歯が上の歯よりも前に出ている状態です。「受け口(うけぐち)」や「反対咬合(はんたいこうごう)」とも呼ばれます。
| 下顎前突の症状 |
下の前歯が上の前歯よりも前に出ている |
|---|---|
| 下顎前突の原因 |
遺伝的な要因 |
| 影響 |
顎の大きさと歯の大きさのアンバランス |
開咬(かいこう)
開咬(かいこう)とは、歯科矯正における不正咬合の一種であり、臼歯部を咬合させた際に、前歯部が接触しない状態を指します。
正常な咬合状態では、上下の前歯がわずかに重なり合うことで、食物を効率的に咀嚼し、発音を円滑に行うことができます。
しかし、開咬の場合、前歯部に隙間が生じるため、これらの機能に支障をきたす可能性があります。
| 開咬の原因 |
骨格性要因/上顎骨または下顎骨の成長異常により、上下顎の骨格的なバランスが崩れることが原因となる場合があります。 |
|---|---|
| 開咬が及ぼす影響 |
開咬は、審美的な問題だけでなく、以下のような機能的な問題を引き起こす可能性があります。 咀嚼機能の低下/前歯で食物を噛み切ることが困難になるため、咀嚼効率が低下します。 発音障害/特にサ行、タ行などの発音が不明瞭になることがあります。 顎関節への負担/特定の歯に過剰な負担がかかり、顎関節症を引き起こすリスクが高まります。 歯周病のリスク/口腔内の乾燥を招きやすく、歯周病のリスクを高める可能性があります。 |
過蓋咬合(かがいこうごう)
過蓋咬合(かがいこうごう)とは、歯科矯正における不正咬合の一種であり、上下の歯を咬み合わせた際に、上の前歯が下の前歯を過度に覆い隠してしまう状態を指します。
正常な咬合状態では、上の前歯が下の前歯に対して適度な被蓋を持つことが理想的ですが、過蓋咬合の場合、被蓋が深くなりすぎている状態。
| 開咬の原因 |
過蓋咬合の発生要因は様々ですが、主な原因として以下のものが挙げられます。 |
|---|---|
| 骨格性の要因 |
上顎の過成長や下顎の劣成長など、顎骨の形態異常が過蓋咬合を引き起こすことがあります。 |
| 歯の位置異常 |
上顎前歯の挺出(歯が通常よりも長く伸びている状態)や、下顎前歯の圧下(歯が通常よりも短くなっている状態)が過蓋咬合の原因となることがあります。 |
| 咬耗 |
歯ぎしりや食いしばりなどにより、奥歯が摩耗し、前歯の被蓋が深くなることがあります。 |
| 過蓋咬合の影響 |
歯ぎしりや食いしばりなどにより、奥歯が摩耗し、前歯の被蓋が深くなることがあります。 |
| 過蓋咬合の影響 |
歯ぎしりや食いしばりなどにより、奥歯が摩耗し、前歯の被蓋が深くなることがあります。 |
歯周病のリスク/下顎前歯が上顎の歯肉に強く接触することで、歯肉に炎症が生じやすくなり、歯周病のリスクが高まります。
顎関節症のリスク/顎関節に過剰な負担がかかり、顎関節症を引き起こすことがあります。
歯の摩耗/上下の前歯が強く接触することで、歯が摩耗しやすくなります。
審美的な問題/前歯が深く覆いかぶさることで、見た目のバランスが悪くなることがあります。
発音障害/舌の動きが制限され、発音に影響が出ることがあります。
正中離開(せいちゅうりかい)
正中離開(せいちゅうりかい)とは、上の前歯の中央(正中)に隙間ができている状態のことを指します。
一般的には、上の前歯2本の間、つまり真ん中に隙間がある状態を指すことが多いです。
この隙間は、必ずしも悪いものではなく、成長過程で一時的に見られることもあります。
しかし、隙間が大きい場合や、永久歯が生え揃った後も隙間が残っている場合は、原因を特定し、必要に応じて治療を検討することが望ましいです。
正中離開の原因はいくつか考えられます。
上唇小帯(じょうしんしょうたい)の発達/上唇と歯茎をつなぐスジ(上唇小帯)が発達しすぎていると、前歯の間に入り込んで隙間を作ることがあります。
過剰歯(かじょうし)/通常よりも多い歯(過剰歯)が、前歯の根の間に埋まっていると、前歯を押し広げて隙間を作ることがあります。
歯の大きさのアンバランス/歯の大きさがアンバランスだと、隙間ができやすくなります。
顎の骨の大きさ/顎の骨が大きすぎると、歯が並ぶスペースが余って隙間ができることがあります。
舌癖(ぜつへき)/舌で前歯を押す癖があると、前歯が前に押し出されて隙間ができることがあります。
上唇小帯切除術(じょうしんしょうたいせつじょじゅつ)/上唇小帯が原因の場合は、手術で上唇小帯を切除することがあります。
過剰歯の抜歯/過剰歯が原因の場合は、過剰歯を抜歯することがあります。
矯正治療/歯並び全体を整えるために、矯正治療を行うことがあります。
自分でできる歯並びチェック
正面からの観察
鏡の前で、上下の歯を軽く噛み合わせた状態で、正面から歯並び全体を観察します。
上の歯の中心と下の歯の中心が一致しているかを確認します。ずれがある場合は、顎の骨格に問題がある可能性があります。
前歯の重なり具合を確認します。前歯が大きく重なりすぎている(過蓋咬合)または、全く重なっていない(開咬)場合は、注意が必要です。
歯並びにデコボコがないか、歯がねじれていないかを確認します。
横からの観察
鏡鏡の前で、横から歯並びを観察します。
上の前歯が下の前歯よりも前に出すぎていないか(上顎前突)、または下の前歯が上の前歯よりも前に出すぎていないか(下顎前突)を確認します。
奥歯の噛み合わせが正常であるかを確認します。
口腔内の観察:
歯ブラシや歯間ブラシを使って、歯の表面や歯と歯の間を清掃しながら、歯並びの状態を確認します。
歯ぐきの状態も確認します。歯並びが悪いと、歯磨きがしにくく、歯ぐきの炎症や出血の原因となることがあります。
その他のチェックポイント
食べ物を噛む際に、特定の歯に負担がかかっていないかを確認します。
発音に問題がないかを確認します。歯並びが悪いと、特定の音が発音しにくいことがあります。
口を閉じている際に、顎に違和感がないかを確認します。
注意点
ご自身でのチェックはあくまで目安であり、自己判断は避けてください。
少しでも気になる点があれば、早めに歯科医師に相談し、適切な診断と治療を受けてください。
定期的な歯科検診を受け、歯並びの状態をチェックしてもらうことが大切です。
5.よくある質問
歯並びが悪いままでいるリスクはありますか?
不正咬合を放置すると、以下のようなリスクがあります。
・虫歯や歯周病のリスク増加/歯磨きがしにくくなり、口腔内の衛生状態が悪化しやすくなります。
・咀嚼機能の低下/食事を十分に噛み砕くことができず、消化不良を引き起こす可能性があります。
・発音障害/特定の音を発音しにくくなることがあります。
・顎関節症のリスク増加/顎関節に負担がかかり、顎関節症を引き起こす可能性があります。
・審美的な問題/容姿に対するコンプレックスを抱くことがあります。
不正咬合が自然に治る可能性は低いですが、早期に歯科医師に相談し、適切な診断と治療を受けることで、不正咬合の改善や悪化の防止が期待できます。
特に、お子様の歯並びが気になる場合は、早めに歯科医院を受診することをお勧めします。