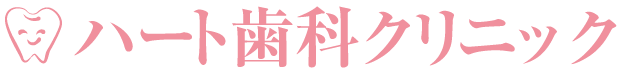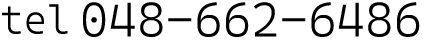今更聞けない虫歯の原因、虫歯対策
改めて虫歯とは?

むし歯(虫歯)とは、ミュータンス菌をはじめとする虫歯原因菌が生成する酸によって、歯の主成分であるカルシウムが溶け出し、歯が脆弱化し、最終的には穴が開いてしまう疾患です。
虫歯は初期段階では、自覚症状が乏しいことが多く、気づかない内に進行してしまう事が多いです。
しかし正しい日頃のケアをしていればほとんどの場合回避できます。
また定期的に歯科健診などにいく事でより健康な状態を保つことができます。
また虫歯の正式には「う蝕(うしょく)」と言います。
虫歯の原因
虫歯(齲蝕)は、複数の要因が複合的に作用して発生する疾患です。
その中でも、特に大きく関与しているのが、糖質(主にショ糖)、原因菌(ミュータンス菌)、そして歯質(エナメル質および象牙質)の3つの要素です。
虫歯の原因

虫歯の原因は糖質
虫歯の発生に深く関与する糖質としては、主に以下のものが挙げられます。
1.ショ糖(スクロース)
一般的に砂糖として知られ、お菓子や清涼飲料水などに広く含まれています。
ショ糖は、他の糖質と比較して、虫歯の原因となる酸を生成しやすい性質を持つため、特に注意が必要です。
2.ブドウ糖(グルコース)
果物や蜂蜜などに天然に存在する糖質です。
ショ糖に比べると酸の生成量は少ないものの、過剰な摂取は虫歯のリスクを高める可能性があります。
3.果糖(フルクトース)
ブドウ糖と同様に、果物や蜂蜜などに含まれる糖質です。ブドウ糖と同様の注意が必要です。
4.麦芽糖(マルトース)水飴や麦芽などに含まれる糖質です。
5.乳糖(ラクトース)牛乳や乳製品に含まれる糖質です。
これらの糖質は、口腔内の虫歯原因菌によって分解され、酸を生成する基質となります。
特に、ショ糖は虫歯菌による酸の生成速度が速く、生成量も多いため、虫歯の発生に最も影響を与えやすいと考えられています。
また、糖質の摂取量だけでなく、摂取頻度や摂取時間も虫歯の発生に影響を及ぼします。
頻繁に糖質を摂取したり、長時間かけて摂取したりすると、口腔内が酸性の状態にさらされる時間が長くなり、歯のエナメル質が溶解しやすくなるため、注意が必要です。
※上記が含まれるものを食す事には問題ありません。
過剰な摂取や摂取した後に歯磨きを行えば問題ありません。

虫歯の原因は歯質?
歯の表面を覆うエナメル質は、人体において最も硬い組織ですが、その質には個人差が存在します。
エナメル質の厚みが薄かったり、構造的な脆弱性があったりすると、虫歯に対する抵抗力が低下します。
歯の形態が複雑であったり、歯並びが不良であったりすると、適切な歯磨きが困難となり、歯垢(プラーク)が蓄積しやすくなります。
その結果、虫歯原因菌の増殖を促進し、虫歯のリスクを高めます。
唾液は、口腔内を中性に保つ緩衝作用や、歯の再石灰化を促進する作用を有しています。
唾液の分泌量が不足したり、唾液の質が低下したりすると、虫歯に対する防御機能が低下します。
フッ化物には、歯質を強化し、耐酸性を高める効果があります。
フッ化物配合歯磨剤の使用や、歯科医院でのフッ化物塗布などにより、歯質を強化し、虫歯を予防することが可能です。
歯の質には、遺伝的な要素も関与していると考えられています。
ご両親が虫歯になりやすい体質である場合、お子様も同様の傾向を示す可能性があります。
これらの要素が相互に影響し合い、個々の歯質が決定されます。
歯質を強化するためには、フ栄養バランスの取れた食生活を心がけ、フッ素が含まれた歯磨き粉を使い、更に歯科検診でフッ素塗布を行う事で強化につながります。

原因菌(ミュータンス菌)
ミュータンス菌(ストレプトコッカス・ミュータンス)は、虫歯の主要な原因菌として知られています。
ミュータンス菌は、口腔内に常在する細菌の一種であり、食物や飲料に含まれる糖質を代謝して酸を産生します。
この酸が歯のエナメル質を溶解することにより、虫歯が発症します。
ミュータンス菌には、以下の特徴があります。
1.高い酸産生能
糖質を分解し、酸を産生する能力が非常に高いことが特徴です。
特に、ショ糖(スクロース)を分解して産生するグルカンは、ミュータンス菌が歯面に強固に付着するための足場となるため、虫歯形成において重要な役割を果たします。
2.酸に対する耐性
酸性の環境下でも生存可能であり、自らが産生した酸によって口腔内が酸性化しても、活動を継続することができます。
3.歯面への付着性
歯面に付着しやすい性質を有しており、特にグルカンを介して強固に歯面に定着します。
4.バイオフィルム形成能
他の細菌とともにバイオフィルム(歯垢)を形成する能力を有しています。
バイオフィルム内部では、ミュータンス菌が持続的に酸を産生し、歯質を溶解させます。
ミュータンス菌は、生まれたばかりの乳幼児の口腔内には存在しませんが、主に親や周囲の大人からの感染によって定着します。
感染経路としては、食器の共有や、食べ物の口移しなどが挙げられます。
ミュータンス菌の増殖を抑制するためには、
・適切な歯磨きを徹底する
・糖分の摂取を控える
・フッ化物配合歯磨剤を使用する
・キシリトール含有食品を摂取する
虫歯になりやすい歯・状態

1.臼歯(奥歯)
臼歯は、口腔内で最も奥に位置するため、歯ブラシの毛先が届きにくく、食物残渣が滞留しやすい傾向があります。
特に、臼歯の咬合面(噛み合わせ面)には、複雑な溝が存在することが多く、歯垢(プラーク)が蓄積しやすい環境にあります。
また、臼歯は咀嚼時に強い力が加わるため、エナメル質が損傷を受けやすく、虫歯のリスクが高まります。
2.隣接面(歯と歯の間)
歯と歯の間は、歯ブラシの毛先が届きにくいため、歯垢が蓄積しやすい部位です。
デンタルフロスや歯間ブラシなどの補助清掃用具を使用し、隣接面の歯垢を徹底的に除去することが重要です。
3.不正咬合(歯並びの悪い歯)
歯並びが悪い場合、歯ブラシが届きにくい部位が生じやすく、歯垢が蓄積しやすくなります。
矯正治療により歯列を整えることで、口腔内の清掃性を向上させ、虫歯の予防に繋げることが可能です。
4.修復物(詰め物や被せ物)の周囲
詰め物や被せ物の周囲には、段差が生じやすく、歯垢が蓄積しやすい傾向があります。
また、修復物が経年劣化すると、歯との間に隙間が生じ、そこから虫歯が再発するリスクがあります。
5.萌出直後の歯
萌出直後の歯は、エナメル質の成熟度が低く、酸に対して脆弱であるため、虫歯になりやすい状態にあります。
特に、小児の乳歯や、萌出したばかりの永久歯は、重点的なケアが必要です。
虫歯になりやすい歯・状態

1.強固なエナメル質
歯の表面を覆うエナメル質が厚く、硬度が高い場合、虫歯原因菌が産生する酸による溶解に対する抵抗性が高まり、虫歯になりにくいとされています。
2.単純な歯の形態
溝が浅い場合、歯垢(プラーク)が蓄積しにくく、歯磨きによる清掃が容易であるため、虫歯のリスクが低減します。
3.良好な歯列
歯並びが整っている場合、歯ブラシが隅々まで届きやすく、歯垢の除去が容易になります。また、歯間に食物残渣が挟まりにくいため、虫歯のリスクを抑制することができます。
4.十分な唾液量
唾液には、口腔内を洗浄する自浄作用、酸を中和する緩衝作用、歯の再石灰化を促進する作用があります。
唾液の分泌量が多い場合、これらの作用が十分に機能し、虫歯になりにくい環境が保たれます。
5.フッ化物の利用
フッ化物は、歯のエナメル質に取り込まれることで、歯質を強化し、耐酸性を高める効果があります。
フッ化物配合歯磨剤の使用や、歯科医院でのフッ化物塗布などにより、歯質が強化され、虫歯に対する抵抗力が増します。
6.規則的な食習慣
間食を頻繁に摂らず、食事時間を一定にすることで、口腔内が酸性状態に置かれる時間が短縮され、虫歯のリスクを低減することができます。
上記の特性を有する歯は、一般的に虫歯になりにくいと考えられます。
しかしながら、これらの特性を有していても、適切な口腔衛生管理を怠らず、定期的な歯科検診を受けることが重要です。
特に、小児の乳歯や、萌出したばかりの永久歯は、重点的なケアが必要です。
虫歯にならないようにするにはどうしたらいい?

虫歯を予防するためには、日々の適切な口腔ケアと生活習慣の改善が重要となります。 以下に、具体的な対策を詳細にご案内いたします。
1.適切な歯磨きの実施
毎食後、少なくとも1日2回以上、丁寧な歯磨きを心がけてください。
歯ブラシの選択、持ち方、動かし方には、それぞれ効果的なポイントがあります。
・歯ブラシは、毛先が細く、柔らかいものを選び、歯肉を傷つけないように注意してください。
・歯ブラシの持ち方は、力を入れすぎないよう、軽く鉛筆を持つように握るのが理想的です。
・歯ブラシの動かし方は、小刻みに、優しく磨くことを意識してください。
力を入れすぎると、歯肉を傷つけたり、歯のエナメル質を摩耗させたりする可能性があります。
・歯と歯の間、奥歯の溝など、歯ブラシが届きにくい箇所は、特に丁寧に磨くように心がけてください。
2.補助清掃用具の活用
歯ブラシだけでは除去しきれない、歯と歯の間や歯周ポケットの歯垢(プラーク)を除去するために、デンタルフロスや歯間ブラシなどの補助清掃用具を積極的に活用してください。
3.フッ化物配合歯磨剤の使用
フッ化物には、歯のエナメル質を強化し、耐酸性を高める効果があります。
フッ化物配合歯磨剤を使用することで、歯質を強化し、虫歯を予防することができます。
4.食生活の見直し
糖分や炭水化物の過剰摂取は、虫歯原因菌の活動を活発化させる要因となります。
間食の回数を減らす、食事時間を一定にするなど、食生活の見直しを行いましょう。
5.キシリトールの摂取
キシリトールは、虫歯原因菌が代謝できない糖アルコールであり、虫歯予防効果が期待できます。
キシリトール含有ガムやタブレットなどを摂取することで、口腔内の環境を改善することができます。
6.定期的な歯科検診の受診
歯科医院での定期的な検診は、虫歯の早期発見・早期治療に繋がるだけでなく、歯石の除去や専門的な口腔清掃、歯磨き指導などを受けることで、虫歯予防に対する意識を高めることができます。
上記の対策を継続的に実践することで、虫歯のリスクを大幅に低減することが可能です。
日々の積み重ねが、健康な歯を維持するために不可欠であることをご理解ください。